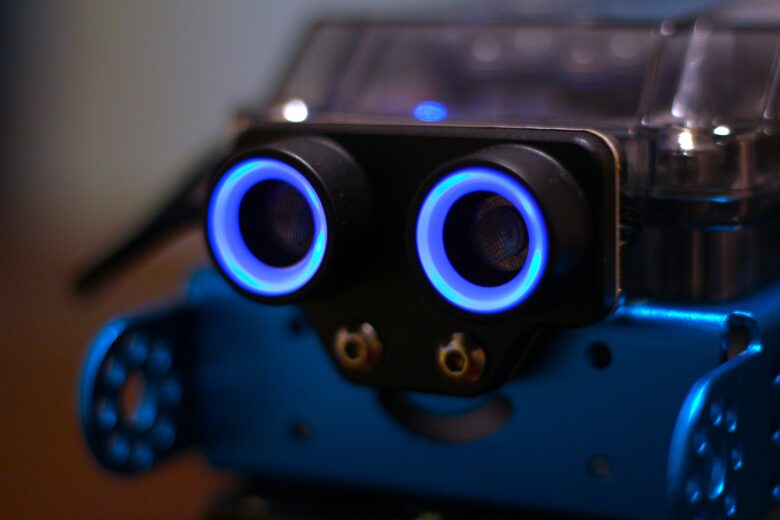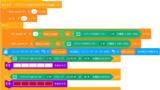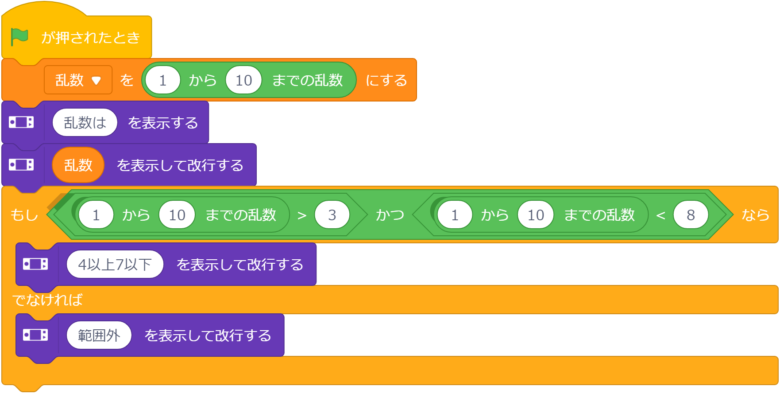今回は、mBot2プログラミングシリーズ(mBlock編)の第4回です。
ここでは「変数」の作成方法とその活用方法について学びます。
変数は、プログラム内でデータを一時的に保存し、再利用するための「入れ物」のようなものです。
特にmBot2のセンサー値を取り入れたプログラミングでは、変数が非常に役立ちます。
この記事で分かること
- 変数の基本的な役割と使い方
- mBlockでの変数の作成方法
変数とは?mBlockで変数を作成するには?
変数に関する説明、およびmBlockで変数を使うための方法はmBotでのプログラミングと同様です。
詳細については以下リンクで説明しています。
簡単な動作プログラム作成
mBot2で変数を使ったプログラムを作ってみます。
変数には、データの一時保管、再利用をする役割があります。
その一例が以下のプログラムです。
『発生させた乱数をCyberPiのディスプレイに表示させ、その値が4未満か5以上かを表示させる』プログラムです。

変数『乱数』を作成し、発生した乱数を格納します。その変数を次の2か所で使用します。
①CyberPiのディスプレイに表示
②条件分岐(5未満かどうか)の判定
実行結果は次のようになります。
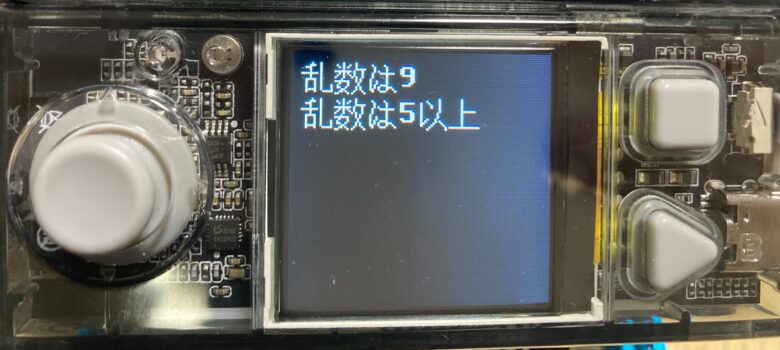
この例は、変数を使用しなければ実現できないプログラムになります。
【例題】変数を作ってみよう
例題1:論理演算で用いる
- 例題
- 解答例
『1~10の乱数を発生させて、4以上7以下の時とそれ以外の時とでCyberPiのディスプレイ表示を切り替える』プログラムを作ってみましょう。
<表示イメージ>
乱数は:〇
4以上7以下 (または) 範囲外
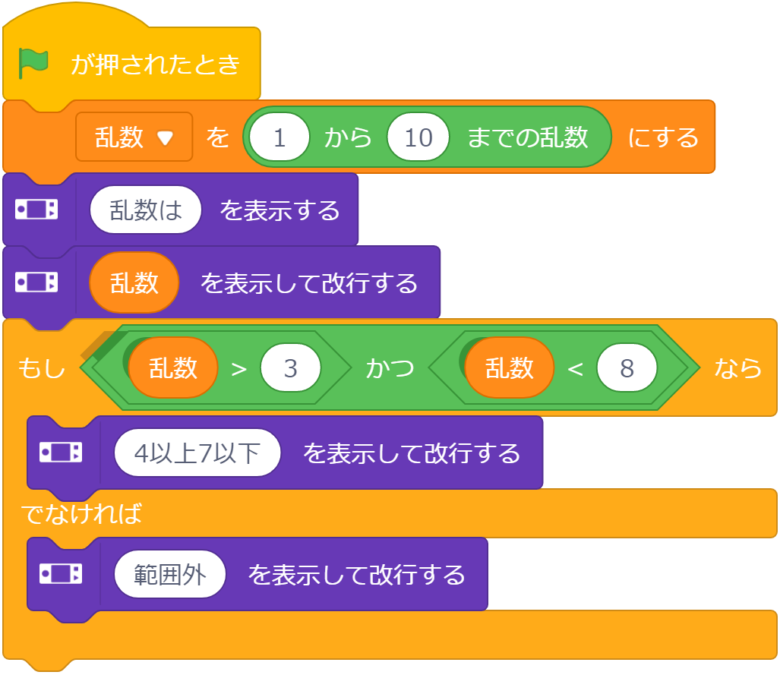
生成した乱数を、変数『乱数』に格納します。
『4以上7以下』の判定は『(乱数>3)かつ(乱数<8)』で表し、条件分岐ブロックで処理をわけます。
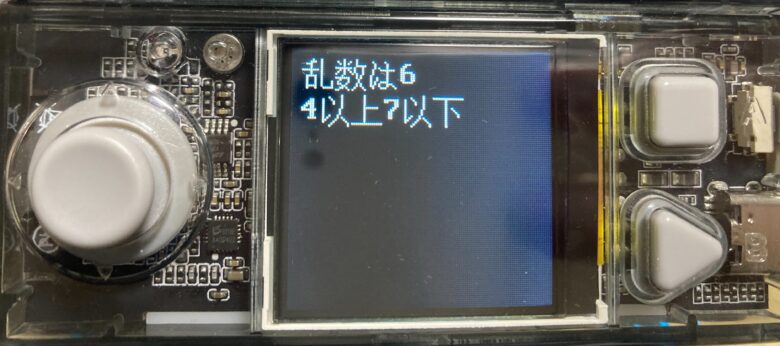
例題2:カウンターを作る
- 例題
- 解答例
『1~5の乱数を10回発生させて、全ての乱数をCyberPiのディスプレイに表示させる。最後に、5が生成された回数を表示する』プログラムを作ってみましょう。
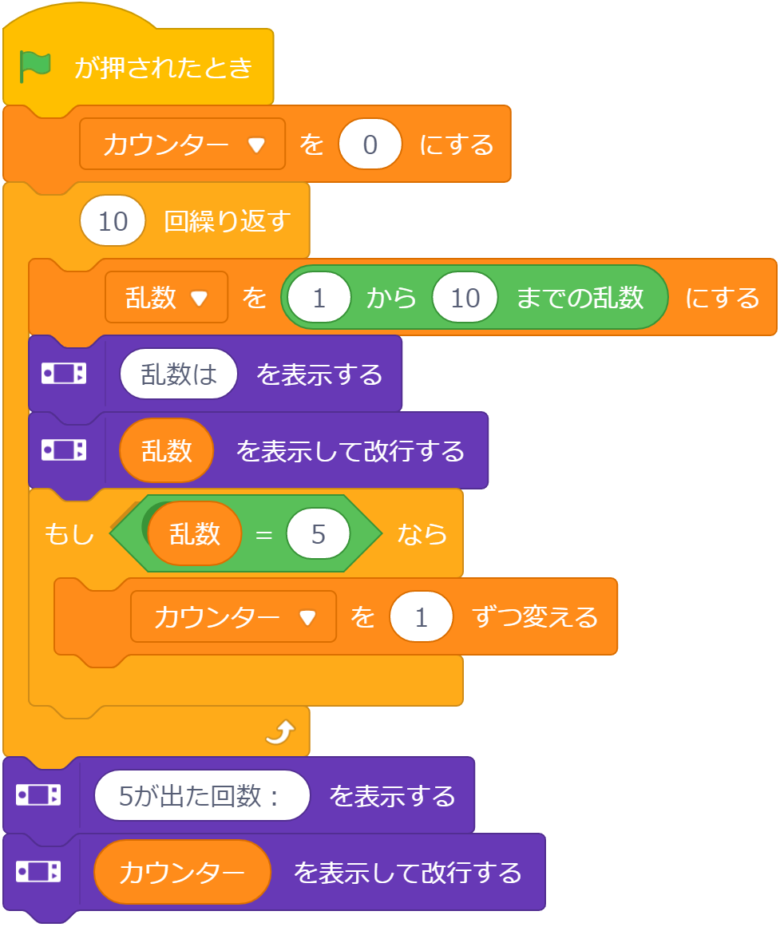
変数『乱数』と『カウンター』を作成します。
変数『乱数』は①ディスプレイ表示、②5かどうかの判定 の2か所で使います。
乱数が5なら、『カウンター』に1を足します。
この処理を10回繰り返すことで、『カウンター』には生成した乱数が5であったときの回数が入ります。
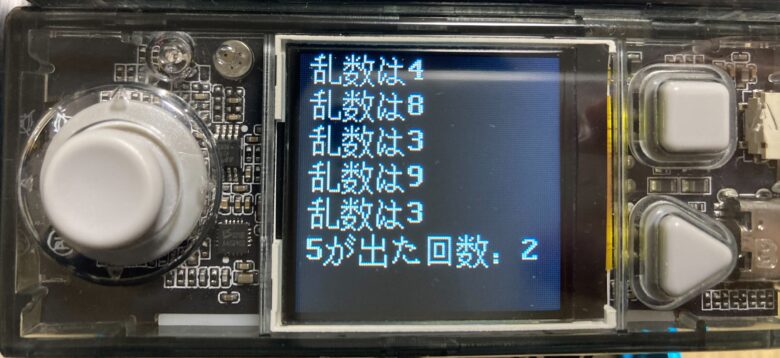
まとめ
変数を活用することで、より高度なプログラムを作成できるようになります。
センサー値を記録し、分析することで、mBot2の動きをさらに細かく制御できるようになるでしょう。
次回は、いよいよ『センサー値』を取り込んだ制御について学んでいきます。
mBlockを使ったmBot2のプログラミング方法を丁寧に解説していておススメです。
CyberPi単体でもプログラミング教育に非常に役立ちます!